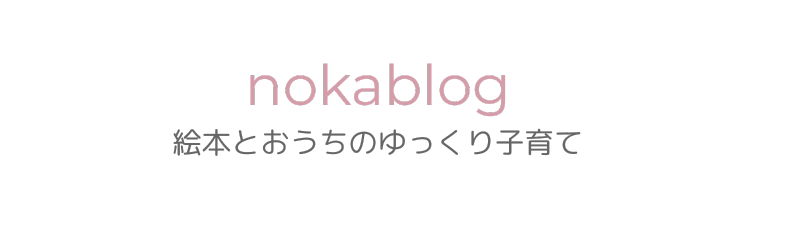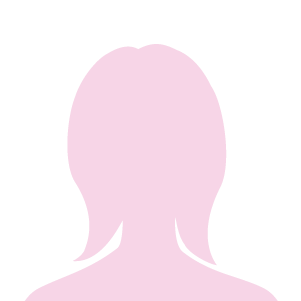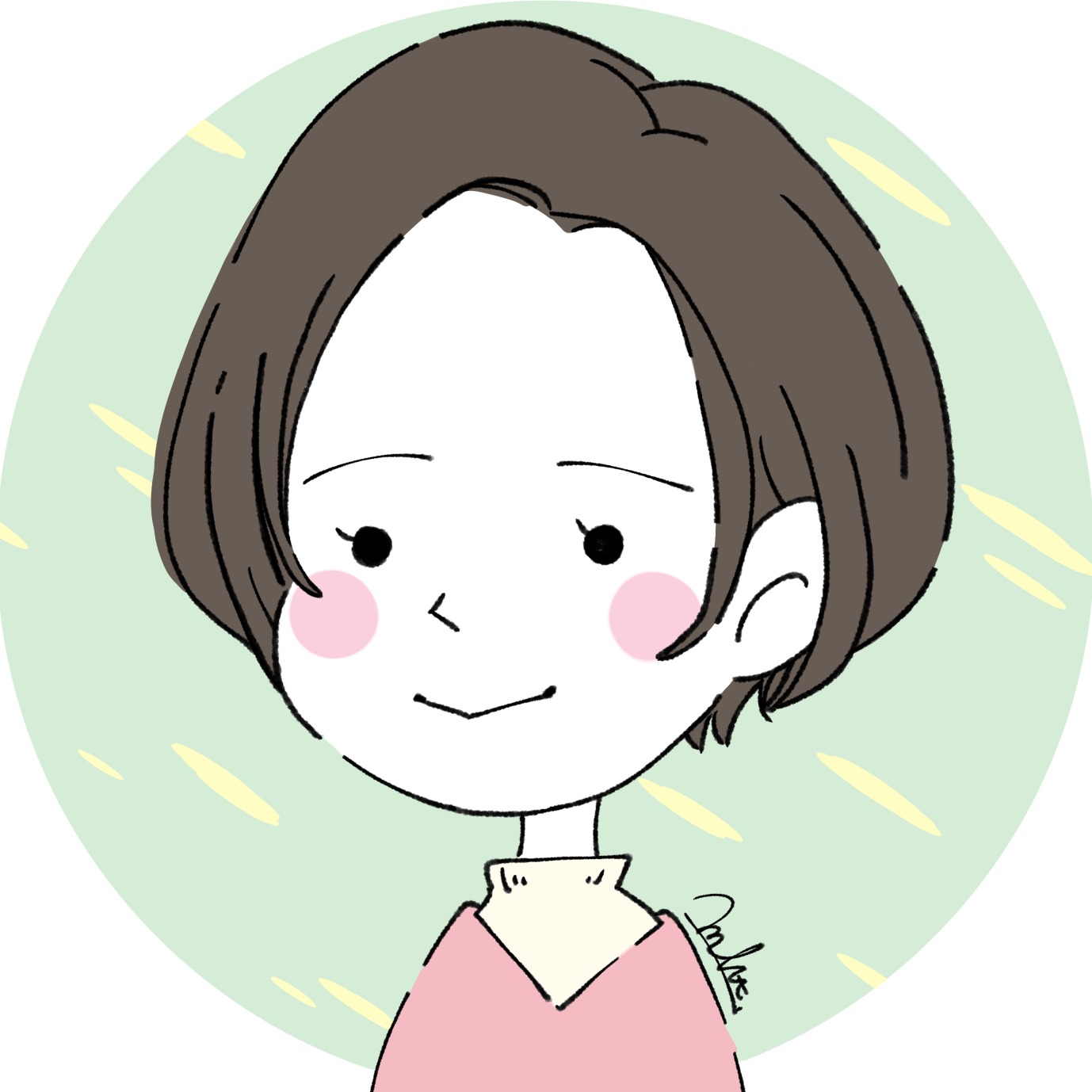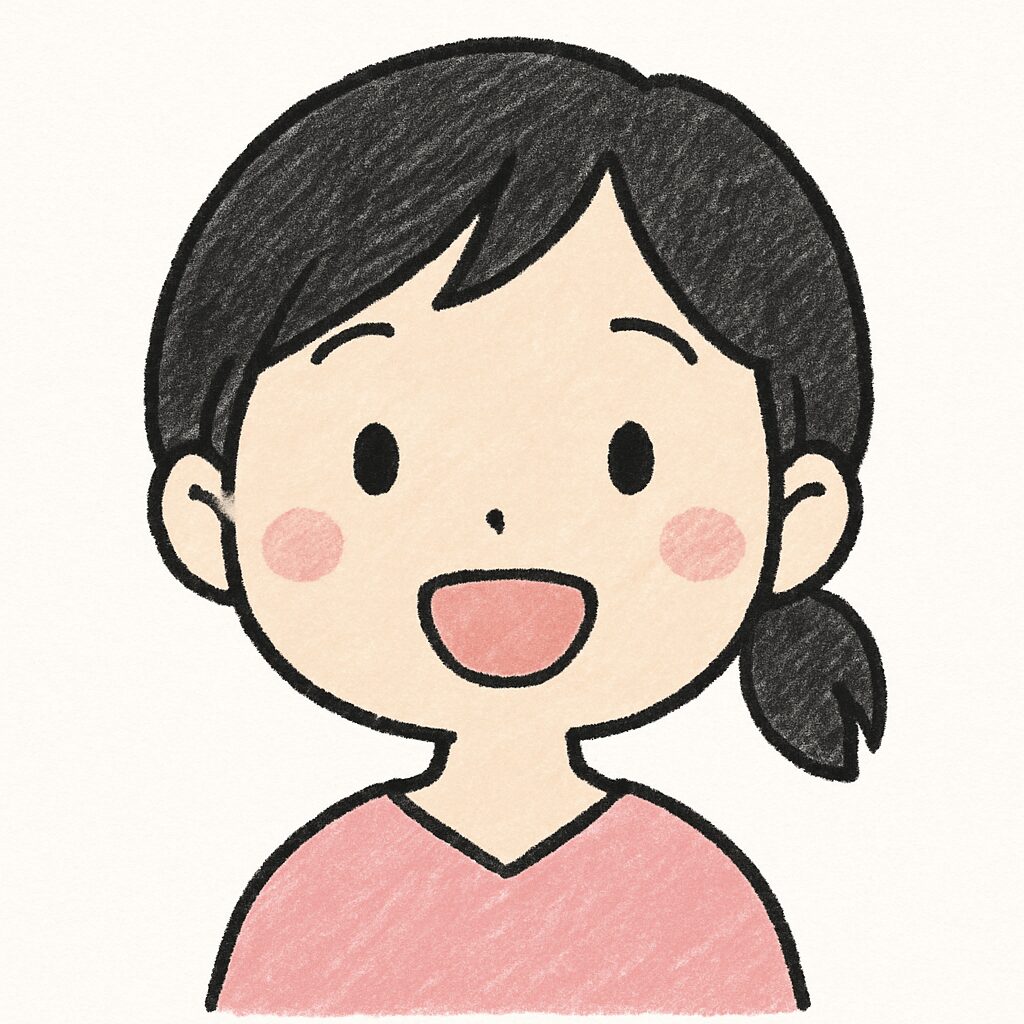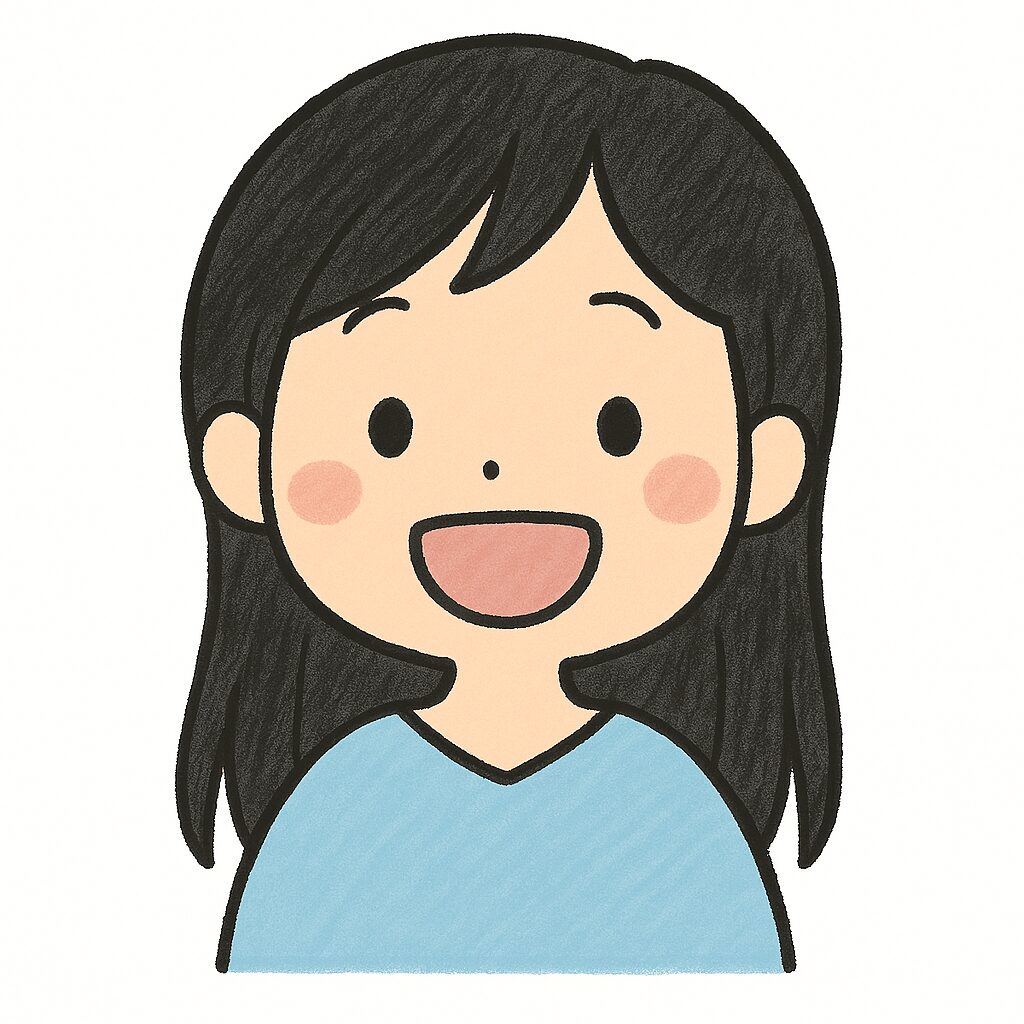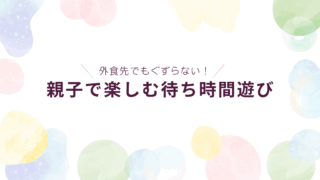6年間毎日絵本を読み続けたら子どもがどう変わったか【実体験】
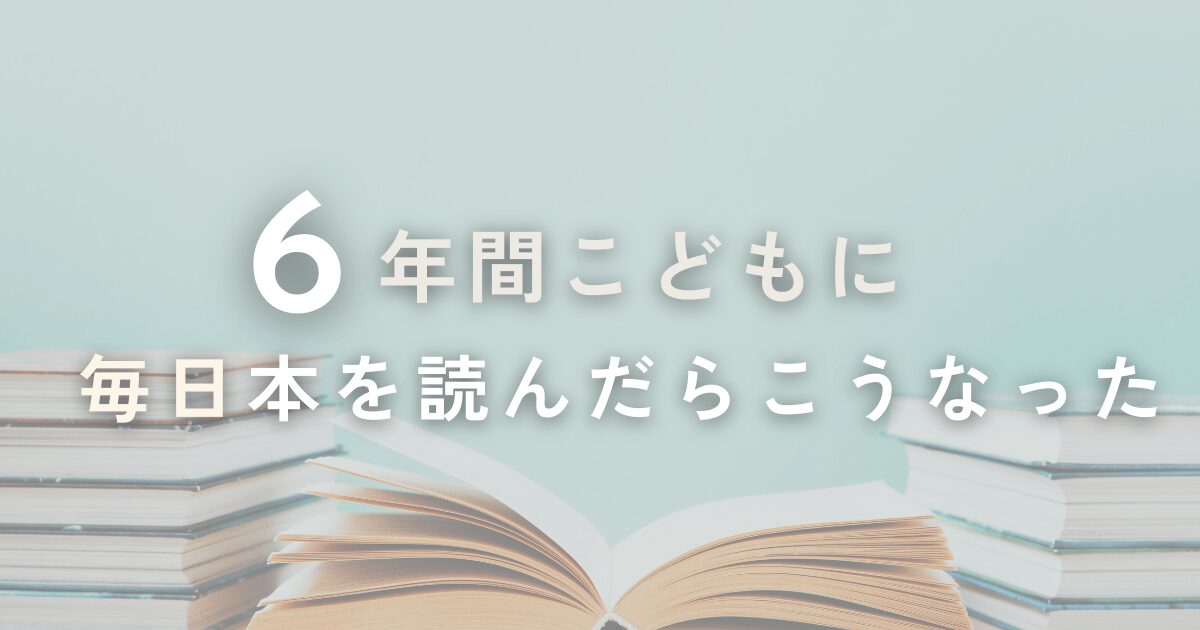
こんにちは!のかです。
毎日子どもと絵本を読んでいるよ!という方。
最近は結構多いのではないでしょうか。
もちろん著者もその一人です。
絵本読むのに全然疲れないし、むしろ家事の手を止めてでも
読んであげたい!っていう方ももちろんいらっしゃると思います。
ある著書には、
「子どもが絵本を読んでと言ってきたときはいつでも読んであること」なんて
書いてあったりします。
でも、現実はそう簡単にいかないこともありますよね。
我が家は長女が6歳、次女が3歳の今日まで、
毎日のように絵本を読んでいます。
体力的に疲れていたり、今は読むタイミングじゃないよ〜と
困り果てたりしたことも多々あります。
それでも「6年間毎日絵本を読み続ける」をやってみて気づいたことを
今日は書いていってみようと思います。
ぜひ最後までご覧になってください。
子どもたちの変化
想像力がふくらむ
ある日、次女がシール遊びをしていたときのことです。
貼ったシールを使って、まるで登場人物のようにお話をつくっていました。
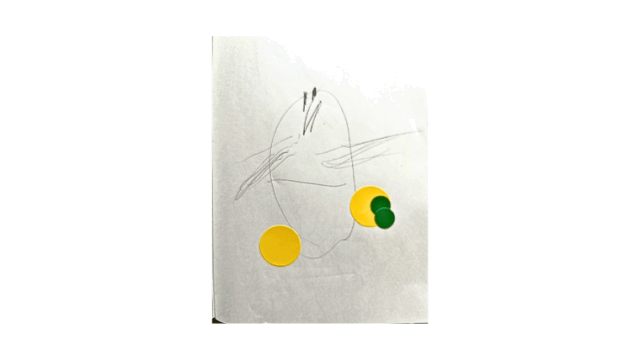
(↑画像が小さくてすみません。中央が人で、シールがおべんとうっぽい絵)
「この子はこうえんであそんでる」「こっちはおにぎり食べる」など、
絵本で見た世界を、そのまま遊びの世界へと広げていました。
感受性が豊かになる

これは、長女が4歳の頃。
我が家は福音館書店「ちいさなかがくのとも」を定期購読しています。
2023年に「あわあわふわふわ!くまのたんくん」が届き、
気に入って何度も繰り返し読んでいました。
ある日、ぬいぐるみを持ってきて、
そんな気持ちを自然に言葉にできるようになっていたんです。
ただ、著者は小さい頃
お気に入りのふくろうのぬいぐるみを洗ったら、
手触りがガサガサのゴワゴワになってしまったという苦い経験を持っています。
もちろん干すときも、洗濯ばさみで吊るすのではなく
ハンガーに寝かせるようにそっと干しました。

(よく洗われるぬいぐるみオールスターズ)
絵本を通して「ものや人に寄り添う心」が育ってきたのを感じました。
くまのたんくんのお話はこんなかんじです↓
主人公のはーちゃんは、大好きなクマのぬいぐるみの「たんくん」を、小さなお風呂に入れてあげました。お湯に浸かると「ぷくぷく」とおならのような気泡を出し、持ち上げると「べっちょり」と重いたんくん。石けんでこすれば「ぶくぶく」の泡に包まれ、タオルで拭くと「ぼさぼさ」に。さらに、おひさまのもとに干してあげると……? 洗うことが楽しくなる絵本です。(福音館書店様公式サイトから引用)
絵本「こんとあき」のこんのぬいぐるみ
絵本に忠実なふかふかのしっぽに
ぽってりしたお耳!
お洋服はほんとうに脱がせてあげることができます。
絵本「フレデリックーちょっとかわったねずみのはなし」のフレデリックのぬいぐるみ
手乗りサイズでふわふわです。
ちゃんと自立するのも飾りやすくかわいいポイントです。
シュタイフ デディベアの「フィン」
長女の出産時にお祝いとしていただいたもの。
抱っこするとくたっとなるところが
子どもたちのお気に入り。
シュタイル さるの「カドリー」
こちらは次女への1歳お誕生日プレゼント。
手足が長いので赤ちゃんの頃から持ちやすく
いつも一緒に遊んでいます。
言葉の幅が広がる

絵本には、
普段の会話では出てこない言葉もたくさん出てきます。
日本語特有の「オノマトペ」なんかも
そうですよね。
気づけば子どもたちの口から、
「とことこ」「ぴょんぴょん」「しんとする」など、
豊かな表現が出てくるようになっていました。
一人で読む力がつく

長女が4歳頃から、一人で絵本を眺めるようになり、
小学生の今では、自然と自分で読む場面も増えました。
「毎日絵本を読んでもらう経験」「絵本がいつもそばにある日常」が積み重なり、読書のハードルが低くなっている
絵本は“日常の入口”

いま思うと、絵本は子どもたちにとって 日常生活や遊びにつながる入口 でした。
お話をきっかけにごっこ遊びが始まったり、
言葉がふくらんだり、
気持ちを伝える練習になったり。
「読む」だけで終わらず、
親子の会話や行動にまで広がるのが、絵本の魅力なんだと思います。
絵本は子どもと一緒に成長する大切なツール

6年間の読み聞かせで感じたのは、
「毎日の積み重ねが、子どもの心をじんわりと育てていく」ということ。
特別な準備は必要なく、
1日1冊でも、寝る前や空いた時間に読んであげるだけです。
その時間が、子どもたちの成長に大きな力をくれたと思っています。
絵本を子どもと楽しむ時間、ぜひおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。